働くこと、つまり労働とは何なのか。
私たちは仕事でいったい何をしていて、
どうしていけばいいのか。
私のオールタイムベストヒット本
内田樹『困難な成熟』より、
働くことの本質について、
まとめていきます。
「答え」は書いてありませんが
働くことについて考えるための
手掛かりになるような内容です。
働くことに対して
なかなか考える手掛かりがなくて
困っている人に紹介したくなるような
話が展開されてるんですよね。
働くってしょせんこんなもんだろ~
という固定観念を揺るがしてくれる
面白さを一緒に体感していただきたいです。
働くことの本質について
日々の仕事に疲弊し、
「なんでこんな辛い事してるんだろう…」
なんて思うことがあるかと思います。
辛いものは辛いけど
生きるためにはやんなきゃならないから、
と割り切って考えないように
するのもいいですが、
働くことが大変な理由には実は
人類史的な背景があって面白いので
ぜひ考えていきたいものです。
労働そのものの本質を知ると
それなりに色々見えてきます。
働くことに疲れる理由
私たちはなぜ働くことに疲れるのでしょうか。
日々の仕事で疲れるなーと思うときを
振り返ってみてください。
現場で長時間肉体労働をした時でしょうか。
一生懸命営業周りをしたとき
でしょうか。
でも案外、そのように価値のあるものを
生産したり、提供して喜んでもらえるような時
ではなくて、
それ自体では価値のないような、
誰も喜ばないような仕事をしている時、
の方が疲れてくるんじゃないでしょうか。
こちらを読んでみてください↓
むしろ、みなさんの疲労感の原因は「どうしてこんな意味のない会議を何時間もやるんだよ」とか「どうしてこんなどうでもいいことをぐだぐだ書いた書類を期限までに提出しなければないけないんだよ」というタイプのものではないんですか?「価値あるものをたくさん作ってください」という要請に僕たちは疲れることはありません。(省略)僕らが疲れるのは「こういうスペック通りの価値あるものを、いついつまでに納品するように。遅れたらペナルティ課すからね」というタイプの要請に追いたてられているときです。人間は生産することに疲れるのではなく、制御されることに疲れるのです。
『困難な成熟』内田樹
いかがでしょうか?
私は事務やってるのでバリバリ思い当たります。
と言いますか、、、
事務の仕事ほとんどこれじゃん!
って思いました。
事務仕事やってない方もこんな感じで、
訳も分からずに追いたてられて
訳も分からず納期に間に合わせなければ
いけない時じゃないでしょうか。
つまり、私たちは「制御されること」に疲れるわけです。
ただ、ここでやっかいなのは、
この「制御」こそが実は働くことの本質
だということです。
本質だからこそ、
そこから逃れられないことが問題になります。
「制御」から逃れられない
やるせなさこそが働くことに
疲れる理由ということになります。
内田さんは働くこと、
つまり労働することの本質について
このように述べています。
労働の本質は自然の恵みを人為によって制御することです。労働の本質は「生産」ではなく「制御」です。人間にとって有用な資源を「豊かにすること」ではなく、それらの資源の生産・流通を「管理すること」です。
『困難な成熟』内田樹
どうですか?
ここで「ん???」ってなりませんか?
同時にここがかなり面白いところだと
思ってるのですが、
「生産」や「豊かにすること」
こそが労働だと思ってたのに、
実は労働の本質ではないんですよ!
産むことではなくて、
「制御すること」が実は労働とのこと…
「労働」って言葉でパッと浮かぶのは、
工場で世の中に役に立つものを
生産することだったり、
豊かになるために新しいものを
生み出すことが仕事の
本質だと思ってましたけど
労働の本質に照らし合わせたら、
そうじゃないらしいです!
なんでそうなってるのかについては、
人間と人間以外の動物を
比べたらわかりやすいです。
人間以外の動物たちは自然に
あるものでやりくりして生きてます。
ライオンはシマウマを捕食しますけれど、これは「ありもの」を消費しているわけです。ライオンはシマウマを飼ったり、交配させたり、飼料を栽培したり、食べ残しの肉をマーケットで売ったりしません。
『困難な成熟』内田樹
「ありもの」を食べて、それでおしまい。
でも人間はそれだけではなくて、
自然の恵みを安定的に受け取れるように、
自然をコントロールするように
なったということです。
人間以外の動物は、
食べ物がなくて飢えることもあるけれど
基本的にはそこに有るもので
なんとか消費をして、事足ります。
でも人間は行き当たりばったりで食えたり
食えなかったりするのはまずいので、
安定供給を望むようになりました。
そして安定して必要なものを得るためには
「制御」や「管理すること」が必要で、
これこそが労働の本質です。
生産されてくるものを「制御」したり、
「安定供給システムを立ち上げ」ないと、
自然の中の動物と同じになってしまうので、
やっぱり労働が成り立つためには
「制御」や「管理」が大前提にあり、
本質というわけです。
働くことは不自然なこと
働くことの本質は「制御」だという
ことですが、
ここで私が思ったのは、じゃあ「生むこと」
や「豊かにすること」はいったい何を
やってるんだ?って思いました。
内田さんのこの文脈でいくと、
それらは他の動物がやってるように、
その場その場で必要なものを調達する
自然に近い営みということになるんですよね( ゚Д゚)
そう言われてしまうと素も子も無い感じがして
あっけにとられるんですが、
でも確かにみんなが豊かになるために
仕事してるんだー
と思いつつ、でもなんか仕事って
そうじゃない気がするのはここら辺が
根底にあるからなんだなーと思いました。
仕事って実は人のためと言うより、
システムのためにやる仕事が多くなり
がちなんだと。
なので、この「労働」ってのは
人間にとっては不自然なことであり、
だからこそ「倒錯」ともいえるそうです。
人間が何よりも求めたのはシステムの安定です。
だから、衣食住のための基本的な財そのものを生産するためのコストよりも、そのような財の生産を安定的に維持できる管理コストのほうに資源を優先的に配分するという「倒錯」が起きたのです。
この「安定供給」ってところが重要で、安定させるためならなんでもやってしまうってところが問題になります。
以下の例を読んだら労働がいかに倒錯しやすい営みなのか見えてくると思います↓
こんな逸話があります。
『困難な成熟』内田樹
むかしアメリカでたいへん出来のよい「じゃがいもの皮むき器」が作られました。どこの家の台所にも行き渡りました。でも、ひと通り行き渡ったところで、売り上げがぴたりと止まってしまいました。シンプルで頑健な作りですし、台所にひとつあれば十分ですから。困った会社はそこで一計を案じました。皮むき器のカラーリングを変えたのです。すると、売り上げがV字回復しました。皮むき器の色をジャガイモの皮と同じ色にしたら、人々が皮むき器をジャガイモの皮といっしょにうっかり捨ててしまうようになったからです。
安定のためなら自社製品を
捨てられてもかまわないと…
なかなか面白いですよね。
便利な皮むき器が出来て
世のため人のためになる仕事をしたのに、
それが大事なのではなくて
生産ラインを安定させることの方が
大事なのでした。
なので、価値のあるものを作る人よりも
その人たちをコントロールする人、
つまり、
仕事そのものには直接かかわって
なかったりする
経営者や管理部門の人たちこそが
労働の本質に近い仕事を
していることになります。
生産コストよりも管理コストのほうを優先するという倒錯は、昨日今日に始まった話ではありません。人類が労働ということを始めた最初の瞬間からずっとそうだったのです。農作業に従事して、価値あるものを作り出している労働者よりも、彼らを監視したり、鞭で叩いたりする人間のほうが「いい服」を着て「いいもの」を食べているというのは昔からずっとそうなんです。
『困難な成熟』内田樹
なんだかやるせない気分に
なりますよね。(-_-;)
倒錯すればするほど
偉くなるシステムの中にいる
ってなんだか滑稽ですよね~
そうであれば、現場で
世のため人のためと思って
豊かなものを生み出している
のは何をしていることになるのか…
大変だけど仕事で
やりがい見つけていきたいな~
なんて考えている私は
一体なんなんだろう、、、
と思わされました。
さらにもう一丁、
「それを言ってしまったらおしまいだ~」
ってなるような一言も引用しておきます(笑)
必要なものを創り出す仕事よりも、不必要なものを創り出す仕事のほうがより労働としては本質的なのです。だから、高額のサラリーが給付され、高い社会的地位が約束される。
これ読んだ時に思ったのは、
営業で売上が右肩あがりに伸びていって、
出世するのを喜んでる営業部は
いったい何に喜んでるんだ…?
ってなったんですよね。。。
まさか不必要なものを売りまくった結果
を喜んでる???( ゚Д゚)
っていう疑問が湧いてきました。
お客様のためになる仕事をしましょう~
なーんて言って、自分たちの仕事に
価値を見出そうとあれこれ努力してるのが
ちゃんちゃらオカシイ…
とでも言わんばかりに労働の本質って
実はあっさり倒錯的なのが強烈でした。
ただし、不必要だけれども
売ってくれたから案外いい
商品と出会えた、とか
人間関係がより豊かになった、、など
付加価値が付いてきて結果的に豊かに
なった人はたくさんいるかと思いますので、
あくまで、あくまで、
「労働ってのはそうなりがちだよ」
という話です。
すべてが倒錯ではないことは
注意しておきたいと思いますー。
でも、このように、
不自然なことと自然なことの間で
葛藤しなが私たちは日々働いています。
自然の近くで働く
働くことに疲れるのは、
働くことの本質がそもそも
人間にとって不自然な営みだからでした。
ここで内田さんが「自然」と「不自然」という言葉を
選んでいるところがポイントになってきます。
なるべく自然に近いところで働くのが
いいそうです↓
身体という自然に絶えず「これでいいんだよね?」と自問しながら僕は労働しています。そこからあまり離れないようにしています。労働する限り、倒錯的であることからは逃れられません。「でも、激しく倒錯的であるか」「ちょっと倒錯的であるか」の違いは、五十歩百歩の違いではありません。ときにその違いは命がけのものになります。
『困難な成熟』内田樹
私たちにとって一番身近な「自然」
は何かと考えたらもちろんこの身体です。
頭でどうすればいいのか考えるより、
「自然」であるこの身体から
考えるということです。
ここでは山や川などの自然の中を
意味するのではなく、
「生きる力が高まるような感じがする」
ことが重要だそうです。
その仕事をしていると、生きる力がなんとなく高まるような感じがする仕事をしてください。「生きる力がなんとなく高まる感じ」とういのはご自身で直感的に判定する他ありません。
『困難な成熟』内田樹
その直観力が無事に育ちますように。
正直なところ、私はまだ
「生きる力が高まる」仕事を
しているわけではないので
実感がないですが、
働くことは本質的に不自然なので
なるべく自然に近いことをして
バランスを取る感じですかね。
内田さんは割と着地点を身体性に
求める傾向があります。
内田さんの著書を読んでいく中で
「身体」がどのような意味をもつかが
見えてくるので、これだけでは
分かりづらいかと思います。
一言付け加えると、合気道を
やっておられるので武道的な
意味合いでの「身体」になりますが、
そこに深入りするのは長くなるので
別の機会にします(^_^;)
でも、少しだけ身体の
「生きる力が高まる感じ」について
言及しますと、
個人と言うより、集団としての身体が
生きてくるかどうかが
ある意味重要になってきます。
この働くことについての章のあとで
組織や集団についての章が続くのですが、
そこで割と「身体」についても語られます。
これまで、働くことにおいて
生きる力が高まりづらい
ことは見てきましたが、
それは「個人」に焦点を
当てた場合の話でした。
ただし、そこから安定供給が望まれ、
労働がなぜ始まったのかを考えると、
それは集団に焦点を当てたからでした。
そもそもなぜ不自然なことをしてまで
安定を求めたのかを考えてみると、
個人が安定して生きるより、
集団が安定して存続していくことに
重きを置いたからです。
集団が、ってところがポイントです。
自分一人ではどうにも乗り越えられないので、
他者の「身体」と同期した方が
「生きる力が高まる」ことを知ったからです。
個人が生き延びる、と考えるより、
集団が生き延びるためには
自分がどう動けばいいのか、
そちらの方にマインドセットすることが
生き延びるための一つの方途であることが
示唆されています。
そのように、単一の身体というより、
複数の身体が同期する感覚
と、身体が「生きる力が高まる感じ」
とが内田さんの身体観においては
共通して重要になってきます。
ただ、集団や組織に関する話は
この辺りまでにして
次回に回そうと思います。
感想
実は制御することこそが労働なのであって、
豊かなものを生産することではない
という労働の本質を知ると、
これまで思っていた
働くことへの見方や
問い方が変わるかと思います。
どれほど豊なものを生産したり、
役に立つことをしたとしても、
構造上このようになっているからこそ
働くことへの「やりがい」とか
そういうのが感じられなくて
何だか違和感を感じるんだな、と
思いました。
別に働くことが不自然だからと
いって、悪いわけではないですし、
やらなければならないことなので
逃れられないわけですが、
ただ、この不自然な営みである
ことを覆い隠さず
不自然であることを認めて、
なおそこから
「生きる力が高まる感じ」が
どんな感じかを問いながら
働いていくと色々開けてくる
かもしれないですね。
内田樹『困難な成熟』夜間飛行、2015年
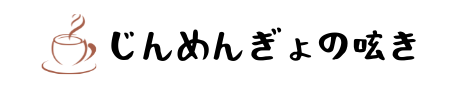
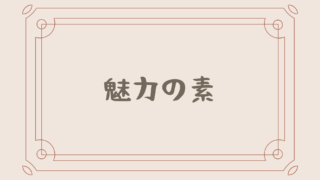
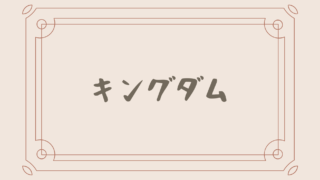
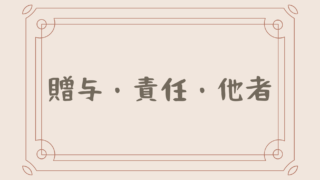
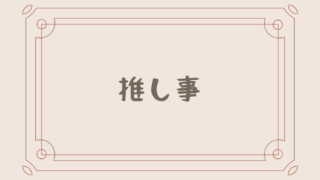
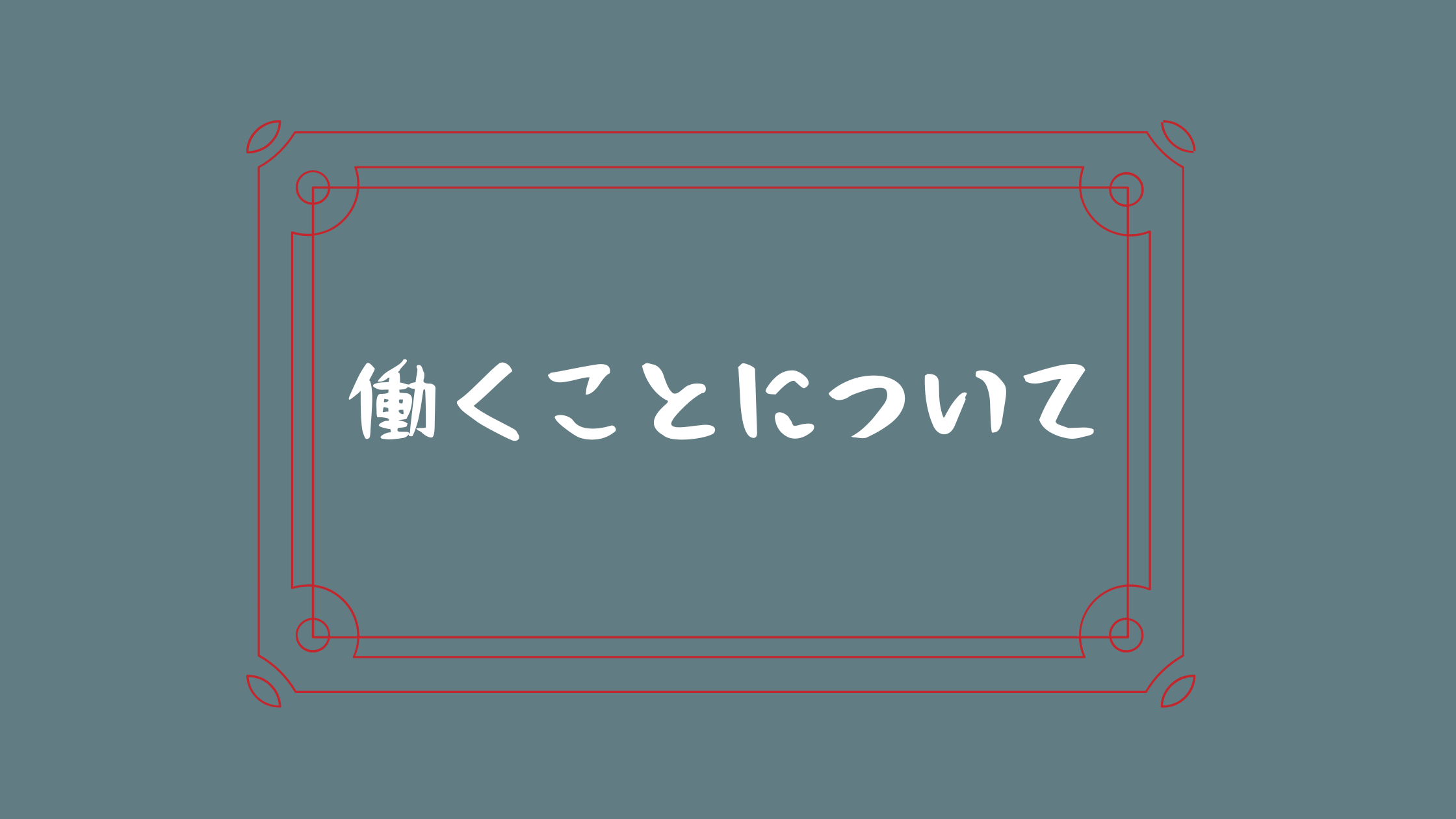

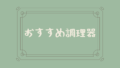
コメント