誰かに対して贈与してしまいたくなる、
与えたくなる、っていったいどういう
ことなのかを考えたい方へ。
「計り知れないほどの贈りものを
受け取ってしまった…」
「自分にはもったいないほど
の贈与を受け取ってしまった。
だからこそなんとか恩返ししないと…」
こういう「ありがたいな~」って
いう思いはどこから来るのだろう?
どうしたら贈与を贈与として
きちんと受け取ることが
できるんだろう?
そこのところが長らく疑問だったので
贈与論を学んでます。
贈与ってそもそも何かって言うと、
お金で買えない、交換できないもの
のことを言います。
人類学や哲学の流れからきてるんですが、
贈与論は元々「モノ」についての理論でした。
つまり贈り物です。
ですが、今回テーマになるのはモノに限らず
言葉や行為など、とにかく
「お金に替えられないもの」全般です。
ノーベル賞とか思い出のある
腕時計とかそんな感じです。
私は割と自分勝手に生きてきた方で、
だからこそ「贈与」とか
「利他」とか「感謝」とか
そういった言葉とは無縁でした(-_-;)
ですが、実際贈与の本質を
突き詰めていくと、
思っていた程単純な話ではなく、
煌びやかな言葉だけでは
表現しきれないほど
奥が深かったです。
贈与と返礼には、
底知れない人間の叡智が
潜んでいることに驚かれると思います。
中でも個人的に贈与論
にハマるきっかけになった本が
ありまして、それがこちら↓
今回の記事はこの二冊に
関する読書記録・読書ノートになります。
と言いますか、、、
結構まとまりのないメモにしか
なってませんがよろしければ
お付き合いください。
恩「返し」ではなく反対給付
贈与論の基本はやはり「反対給付」
にあると思っています。
基本であり、かつ一番面白い
ところです。
どこがどう面白いかといいますと、
受けた贈与はもらった相手に
直接返されるわけではない
というところです…
これが一番ショッキングでした。
恩をもらった人へ直接
恩返しするわけじゃないんですよ!?
衝撃的じゃないですか!
どういうことなのか。
一度落ち着いて考えてみて欲しいんですが、
もし恩人に恩をきっちり返せるのであれば
相手に返したらそれでキレイさっぱり
終わりってことになります。
でも計り知れないほどの
恩があるのにきっちり返せて
しまうのはおかしいわけです。
もし返せてしまったら
計り知れなくないので。
そういうわけで、贈与されたものは
贈与してくれた相手に
直接返そうと思っても返せないんです。
でも負い目を感じるほどの
贈与を受け取ってしまったわけなので
手放さないと自分で持っているのは
手に余る感じがする…
じゃあ、贈与を贈与のままに
手放すためには
どうすればいいでしょうか?
それはズバリ、
“次の人にパスする”
これ以外にもらった恩を
自分の手元から放つ方法はありません。
そして、これが「反対給付」です~
贈与は返せてしまったら
交換になってしまうので、
それは返すものではなく
自ずと次にパスされる働きを
誘発してしまうというイメージです。
なんとなく反対給付伝わりましたか?
これに関して身近な例を持ち出すと
親子愛の例が挙げられます。
親子愛の例
親が子どもを愛すのに、
根拠はありません。
もし根拠があって、
愛す目的があればそれは
愛とは言われません。
なので、親からの無償の愛を
受けた子どもは
根拠はなにも無いにもかかわらず、
育ててもらったので
「負い目」を感じます。
(無意識的な場合や後から
気づく場合もあります)
ですが、根拠無く不当にもらってしまった
ため、子どもが親にお返しをしよう
と思っても、その分をそのまま返す
ことは難しいです。
不当な程、あるいは不合理なほど
のものを受け取ってはじめて贈与に
なるわけなので
もらった相手に直接恩を返すことが
できたとしたら、それは
交換になってしまいます。
せいぜい父の日、母の日に
プレゼントしたり、ちょっとした
家事手伝いをするのが精一杯かと思います。
もし、子どもが親にもらった分だけ
お返しできると思っていたり、
親に裏心があって子どもを育てた、
とかのパターンがあるとしたら、
それは愛や贈与ではなく“交換”になります。
等価交換です。
では、贈与を受け取ってしまって
「負い目」を感じている側は
どうしたらいいのでしょうか?
子どもの例で言えば、
”自分が親となって自分の子どもに
愛を与えること〝
これです。
自分が渡した贈与が、さらにその先へ
パスされたそのこと自体がまさに
相手にとっても贈与になります。
自分の贈与がさらにその先の受取人に
パスされたのであれば、
間違いなく自分の贈与は
正しく受け取られた
ということが分かるので…
つまりは孫の存在こそが親にとって
は贈与の返礼になるわけです。
サンタクロースの例
親から子への贈与の話で
もう一つ身近な例が挙げられます。
サンタクロースと
クリスマスプレゼントの事例です。
もうサンタの奥深さといったら!
煙突から現れる不審者
の話がなんでこんなに世界の親子に
取り入れられてるのか
ここを抑えておくと
毎年のクリスマス楽しく
なります~
でもその前に
贈与にも難しいところが
ある、という話をします。
それは、贈与の差出人が分かって
しまっていたら、呪いになりやすい
ということです。
受け取った側が返礼しなきゃと
思うのは、
割と個人的な気持ちとは関係なく
もっと原理的なものです。
お返ししたくなるのは
個人的な気持ちの問題も
あるにはあるかもしれませんが
人としてなんとなく
そういうものだから
するっていう方が強いはずです。
なのでお返ししなきゃと
思いながらも
そこから返礼をする気持ちが
いまいち無かったり、
物理的、原理的に
お返しがそもそもできない
場合ってありますよね。
例えば、個人的な例を
挙げれば、
私は今、会社勤めを
していますけど、新卒採用で
今の職場に入っています。
私になにがしかの役立つ能力が
あったからでは無いですし、
取り立てて優れた
技能があったわけでもなく、
「可能性」ってもの
に期待して採用してくれてます。
(↑知りませんよ、本当のところは。
新卒採用はその場合が多いから
そう思ってるだけです)
ですが、正直貰ってばかりで
仕事で返せてる感じが
まったくしません。
何年経っても(もう5年目)
未だに仕事で大きな結果を
出せていないと感じています。
いつまでも返礼に値する
大きな結果を今の自分の能力で
出すのは難しいと感じています。
これがいわゆる贈与の「呪い」
なのですが、
返礼の義務を会社に対して
感じていながらも
今の下っ端にとどまる
能力しかない私には
なかなか「お返し」する
目途が経ちません。
負債をいつまでも抱えるんじゃないか
という不安があります。
こういう場合に贈与は
呪いになるんです。
では、この贈与による呪いを
発生させないためにはどうすれば
いいでしょうか?
ここでサンタクロースのシステムに
戻ります。
つまり、
“自分が贈与の差出人であることを
名乗らない”
ということです。
クリスマスプレゼントは親から子へ
渡されるものですが、
親は贈与者として名乗りを
挙げません。
その代わりにサンタクロースという
不可思議な存在を差出人にしています。
しかもサンタは贈り物を
置いていったらすぐに去ってしまうし、
いったい何者かわからない
という存在です。
サンタは子どもが親に対して
返礼できないようにした
システムです。
そして、誰にも返礼できないので
子どもは必然的に次へパスする
ことになり
クリスマスという行事は
そのまた子どもへ
引き継がれていきます。
こんな感じで贈与は
渡す側、差し出す側が
「名乗りを挙げない」という
かなり倫理的な態度が求められるわけです。
このことから分かるように、
贈与はやっぱり受け取る側の論理
ということになります。
「あれは贈与だった」
と分かる受取人がいることで初めて
贈与になるという話です。
差出人のいる贈与は呪いになる
ため、差出人はそれが贈与である
ことを渡す相手になるべく知られない
ようにします。
サンタクロースを出してきたり、
渡した直後に贈与だと悟られないように
「時間差」を生み出したりします。
なので、かなり受け取り手
の「贈与に気づく力」
あるいは、知性が必要になってきます。
じゃあ、どうしたら私たちは
きちんと贈与を受け取る
ことができるのでしょうか?
いかにして贈与は立ち上がるのか…
この問いこそが一番の焦点になります。
贈与はいかにして立ち上がるのか
私たちはどうしたら
贈与に気づくことができるのか。
そもそも贈与は不合理なほど
受け取ったと思った人が
いて初めて成り立つのでした。
では、不合理さを感じる時は
どのような時でしょうか。
それは合理的だと思っていたことの
中に、理論では説明のつかないものが
混ざっていた時かと思います。
つまり、不合理なほどの贈与に気づくためには、
逆の合理性が分かっていないと
そもそも気づけないということです。
見返りが無いのに、
何故この人は私にこれほど
尽くしてくれるのだろう?
根拠がないのに子どもとして
生まれてきたってだけで
愛してくれるのは何故だろう?
このような問いが自ずから
湧き出てくるためには、
ある程度の合理性と
合理性の運動としての交換が
どんなものかを知っていなければ
なりません。
なので贈与というのは、それ
単独で成立するものではなく、
あくまで交換経済(あるいは資本主義)
の「すきま」から見出されるものです。
でも、このような「すきま」から
不合理なほど与えられたとしても
なぜそれを単に「不合理だなー」
で終わらせず、次にパスしたく
なるのか、、、
ここが最大の疑問かと思います。
そして、ここからが
贈与論の「奥が深い」部分です
ので集中して読んでください(笑)
サンタの例に戻るのが一番
いいかと思うのですが、
子どもはある時を境にサンタは存在
しないことに気づきます。
と同時に、
ある大事な事にも気づきます。
それは、
自分の親たちが個人的な意図を超えた
もっと大きな意志に突き動かされて
サンタを代行していたのではないか
という予感です。
なぜ世界中の親たちが
こぞって自分の子どもに
サンタの話を作り上げてまで
プレゼントを渡すのか?
その不合理を合理化しようとする
ことからくる予感なのですが、
これは個人を超えて、
もっと集団的で、人類史レベルの
ルールに従って行動せざるを得ない
人間の本質みたいなものです。
そういう、なんだか分からないけれど
もっと大きな「他者」が私たちに
語りかけてくる、、、
しかも、大事なのは、
その「他者の語り」というのは
自分や自分の親にだけでなく
ずーっと昔から長い時間をかけて
連綿と受け継がれて来たんじゃ
ないかと発見することです。
連綿と受け継がれてきた。
だからこそ自分も次へ
贈与をパスしなければと
思うわけです。
しかも、その「他者の語り」ってのは
かすかなもので、
不合理に気づいて
しかもそれが受け継がれてきた
ことにまで考え至らなければ
到底聞こえてこなかった
語りなわけなので
自分がパスを繋がなければ
ここで途絶えてしまうという
切迫感もあるんです。
遥かな昔から連綿と続く
かすかな「他者の語り」
これを発見することで
贈与が立ち上がります。
読書のすすめ
以上、贈与論の反対給付について
私が面白いと思った部分を
まとめてみました。
二冊ともまだまだ贈与に関する
興味深い話が沢山あるので是非
手に取って読んでみて下さい。
今回は親子とサンタに絞りましたが、
『世界は贈与でできている』では
シャーロック・ホームズや
テルマエ・ロマエなど
私たちが反応せずにはいられないような
例えを持ち出して贈与を語っておられるので
おすすめです。
また、『困難な成熟』に関しては
サンタのとこしか今回参考にしてないので
これだけだと思わないでください!
他にもワクワクするような
理論が盛り沢山です。
特に責任とは何か、労働とは何かについて
めちゃくちゃ考えさせられるので
是非。
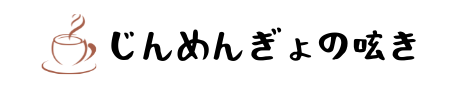
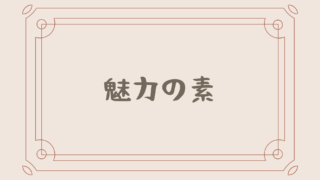
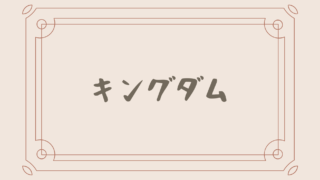
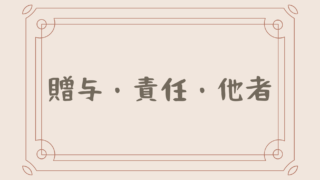
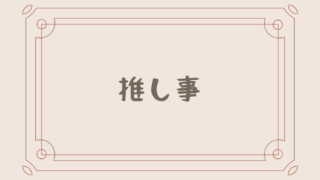






コメント