前回に引き続き
内田樹さんの「労働」に関する
考え方をまとめてみます。
前回の記事↓
前回、
働くことは集団的な営みで、
それについては次回に続く…
なんて書きましたが、
内田さんの労働と
集団性について語る前に、
是非とも触れておきたい
テーマがあるので
今回はそれについてです。
それは何かというと
消費者マインド
に関する話です。
「消費者マインド」は
商品を購入する側の思考のことで、
これは働く側の
マインドとは正反対の考え方を指します。
ここを経由した後の方が、
働くことが集団的な営みだった
と気づきやすいんじゃないかと思いまして、
今回取り上げようと思いました。
このマインドで
働いてしまっている人(若者?)が
多いと内田さんは指摘していて、
私も、働くことが辛くなる
原因の一つでもあるんじゃないか?
と思っています。
なので、
「消費者マインド」はどんな思考で、
働く時にどんな弊害があるのか。
これが今回のテーマです。
あと、
今回は『困難な成熟』のみならず、
内田さんの色んな本から
ヒントをもらいました。
消費者マインドとは
「消費者マインド」は要するに
お客さんのマインドです。
具体的に
どういうことかと言うと、
私たちが買い物をする時のことを
思い浮かべてみると
わかりやすいです。
買い物するとき、
私たちが何を大事にしているか
考えてみてください。
その場で迅速に商品を手に入れて…
自分が差し出した金額と等価の商品を…
しかも間違いなく自分個人宛で…
というこの3つの条件で
商品をゲットすることが
買い物をする時の前提になっている
んじゃないでしょうか?
いわゆる「経済合理性」という
やつです。
コストパフォーマンスを追及している
とも言えるかもしれません。
これがお客さんの思考であり、
「消費者マインド」です。
であれば、このマインドの
一体どこか問題なのでしょうか。
それは、
買い物のときだけなら
いいんですが、
それ以外のところでも
このマインドを適応しようとする
ところに問題が生じます。
とりわけ内田さんは教育の場
と労働の場にこのマインドが
持ち込まれる傾向に対して、
警鐘を鳴らしています。
ここでは、
働いている時に「消費者マインド」を持ち込むことが
どのように弊害となるのかをみていきたいと思います。
消費者マインドの弊害
仕事をする時に消費者マインドを
持ち込むとどうなるのでしょうか。
以下引用です。↓
労働を経済合理性の枠内でとらえると、労働者は自分の労働の成果に対して、「等価」の報酬が、「遅滞なく」、「固有名宛」に給付されることを望む。
『ひとりでは生きられないのも芸のうち』
先ほど、
私たちがお客さんでいる時に
大事にしている前提を
3つ挙げましたが、
その3つを自分の仕事に対しても
当てはめようとしてしまうわけです。
自分が差し出した分の
労働力に対して
等しい量が
返ってくるか(等価交換)とか、
報酬や評価などを
即時得られるのかとか、
ちゃんと間違いなく
自分宛で報酬が得られるのかとか、
そういう「お客さん」の目線で
自分の仕事を見てしまうわけです。
もう少し具体的にどうなるのか
詳しくみていきたいと思います。
等価に遅滞なく
自分が差し出した分と等しい分の
報酬がもらえるかどうかが
買い手にとっては
大事な条件の一つでなのでした。
いわゆる
等価交換の原則です。
でも、この等価交換の原則は、
商取引の場を成り立たせるために
便宜的に用いているものであって
すべてに当てはまる原理じゃない、
というところがポイントです。
本当に便宜的で一時的な
マインドなんですよ。
一方、働くことは等価交換ではなくて
割と「贈与」の要素が強いんですよね。
差し出した分だけ
返ってくるとは限らないんです。
等価交換の原則を働くことに
当てはめてしまうと、
自分の努力した分
が適切に評価されたかどうかとか、
周りと比較して
自分の働きが十分評価されているか
を気にするようになります。
なので、つい
「私はしっかり仕事しているのに
アイツは手を抜いて仕事していて、
なのに給料が同じなのはオカシイ…」
というようなことを思ったり、
逆に
「手を抜いて
少ない労力でやり過ごしてやる!」
なんてことを考えかねないんです。
そして最終的には割に合わない
ので働くことを放棄するんです。
「なんだか働く気がしないなー」
と思っていたら、
こんな感じで自分の取り分を
商取引の原理で捉えているから
かもしれません。
消費主体は、自分の前に差し出されたものを何よりもまず「商品」としてとらえる。そして、それが約束するサービスや機能が支払う代価に対して適切かどうかを判断し、取引として適切であると思えば金を出して商品を手に入れる。(…)そして、この幼い消費主体は「価値や有用性」が理解できない商品には当然「買う価値がない」と判断します。
『下流志向―学ばない子どもたち 働かない若者たち―』
商取引をする感覚で、
自分が差し出した労力に対して
適切な報酬が与えられるのかどうか
を一番に考えてしまう、
というのが「消費主体」です。
でも、働くことってそうではなくて、
等価の報酬が得られるかどうかは
その場では分からないわけです。
しかも、
大体の価値が見えていたり、
報酬が約束されていたとしても
それらは一度働いてみて、
ある程度時間が経った後に
もらえたりするものでもあります。
でも時間がかかることを嫌がり、
「即時」「すぐに」
欲しがることから
「消費者マインド」で
考える人は、時間の感覚が
異なっていると内田さんは指摘します。
労働を消費行動のスキームでとらえる若者たちが「労働からの逃走」の道を進むのは、彼らが時間を勘定に入れ忘れているからだと私は考えています。
『下流志向―学ばない子どもたち 働かない若者たち―』
だから、賃金は原理的に常に不当に安いということになります。それはどう見ても等価交換には思われない。なぜなら、自分が会社やクライアントに対して差し出した「苦役」に対して、「それと等価の報酬」が同時的に与えられていないからなのです。
「同時的に」ってところが
ミソなんですよね。
商取引の場面では
自分がお金を出したら
その場ですぐ商品と
交換できる場合が多いですけど
働いている場合、
すぐには与えられないです。
いつもより頑張って、
周りより多めに働いたとしても
自分の欲しかった周りからの評価や、
頑張って働いた分の給料UPなどは
何年も先だったりするわけです。
でもそれもそのはずで、
冒頭でも働くことは
「贈与」に近いと言ったように
個人が受け取る分より
余計に働いてくれた分、
つまりは余剰によって
会社や組織は利益を得ています。
でもってその利益の余りで
市場全体がうるおって交換を
促す、っていう流れがあるわけです。
余剰で経済、市場がまわるわけなので
根本的に労働っていうのは
交換というより贈与なんですよ。
労働に対して賃金が安いというのは原理的には当たり前のことだからです。賃金というのは労働者が作り出した労働価値に対してつねに少ない。(…)そこで生じた余剰が、交換を加速してゆき、その結果、市場が形成され、分業が始まり、階級や国家ができあがる、というかたちで人間社会は作られてきた。
『下流志向―学ばない子どもたち 働かない若者たち―』
常に自分の差し出した分より
報酬は少なく返ってくる…
なぜなら余剰分が
交換にまわされているからです。
というわけで、
働くことは自分個人のために
するものではなくて
会社や市場経済全体が
うまく回っていくために
することなのでした…
でもなんでわざわざ私たちが
市場経済やらのために贈与しなければ
ならないんでしょうか?
それは私たちが
生まれた時からもうすでに
どこかの誰かが整えてくれた
経済システムの恩恵に
あずかっているからです。
その「お返し」として
私たちは働いていかなければ
ならないから
働いて
贈与しなきゃならないんです。
…納得いきませんか?
私もあんまり実感ないんですけど(-_-;)
内田さんはそういう着地点で
書いておられることが多いので、
こういうのは
もっと色んな経験をして
「大人」になったら分かるのかなー
という姿勢でいればいいのかなと思います!
労働はほんらい「贈りもの」である。すでに受けとった「贈りもの」に対する反対給付の債務履行なのである。
『ひとりでは生きられないのも芸のうち』
「反対給付」っていうのは
等価交換ではない
お返しのようなものだと
思っておいてください。
結局、自分がどれだけ受け取っていて
「お返ししていかなきゃならない!」
っていう、感覚があるかどうかが
問題なんだなと思います。
「消費者マインド」だけで
考えると
自分が色んな人に支えてもらって
成り立っていると
気づいていないところが
つまづくポイントなんだな
と思いますよね。
でも確かに割と贈与で成り立ってる
ことって多くて、例えば
頼まれてもいないのに
私たちは赤ちゃんの頃から
育てられて世話してもらいましたし
(愛情のある育て方されたかはさておいて)
道路だって歩きやすいように
あたりまえのように整備されて
食事の準備をしようと
思ったらスーパーに行けば食材に
ありつけるわけなので
もう本当に私たちは先人たち
の働きの成果を受け取り
まくってるんですよ。
そう考えると確かに、働くってのは
個人対個人で完結する
ものではなくて
集団全体が
うるおうためなんだな
という気がしてきますよね。
個人宛で
先ほど、
働くことは集団の営みであることを見てきました。
労働は本質的に集団の営みであり、努力の成果が正確に個人宛に報酬として戻されるということは起こらない。(…)個人的努力にたいして個人的報酬は戻されないというのが労働するということである。個人的努力は集団を構成するほかの人々と利益を分かち合うというかたちで報われる。
『ひとりでは生きられないのも芸のうち』
働いて得た報酬は、個人に
共有されるのではなく、
集団のみんなに共有されるものなんだ
と言われています。
確かに、最終的に個人宛で
お給料はもらえますけど
もともとの宛先は集団なのであって、
それを便宜的に個人に
分配するから個人宛である
かのように見えるんですよね。
先ほどの繰り返しですが、
働くことが集団の営みなのは
働いた余剰も報酬も
両方とも
集団に回されるからです。
分かりにくいですけど
現にそうなっているので、
「消費者マインド」でいるより
集団としてのマインドセットをした方が
働きやすいことがわかると思います。
とは言われても
やっぱりそんな集団的なことしてる実感がないし、
中々納得いかない!
という人のためにもう一つ
内田さんがよく出される
だんご作りの話をあげます。
本来、「自分の仕事」と「他人の仕事」のあいだには境界線などない。それをむりやり区切ろうとしたら、仕事をセグメント化、モジュール化するしかない。「たしかにこの仕事は隣の人と間違えようがない」というくらいにきっぱり識別できる仕事というのはその仕事自体はきわめて均質的なものにならざるを得ない。喩えて言えば、それまでいっしょに「だんご」を作っていたのを止めて、「今日からオレは餅だけこねるから、おまえはあんこだけ作れよ」というようになると、たしかに餅の生産高や品質は「オレ」の成果として明確に外形化される。「餅はうまいがあんこはいまいち」という評価を受けた場合も、ぜんぜん気にしないでいられる。けれどもその代償として「一生餅だけこね続ける」という呪いをかけられる。
『ひとりでは生きられないのも芸のうち』
本来仕事に境界線はなく、
責任の所在を明確にしたり、
ここにあるように自分の仕事の評価が
自分に直接宛てられるようにするために
あえて区切って個々人の仕事
として割り振っています。
自分と他人の仕事の成果が
目に見えてわかるように
分業にすることで
分かりやすくなるしそれで
いいじゃん
って思うかもしれませんが、
内田さんが指摘しているように、
それだと
「一生その仕事をやりつづける呪い」
がつきまといます( ゚Д゚)
要は、割り振られた仕事を
超えようと思っても超えられず
ずっと割り振られた「自分の仕事」だけを
することになりやすい、ということです。
限られた仕事だけに限定される
状態は自然な状態じゃないですよね、
なので、やっぱり本来仕事ってのは
「自分の仕事」「他人の仕事」
に限定されないものなんです。
その証拠にどれだけ
「自分の仕事」と「他人の仕事」
というふうに切り分けたとしても、
どうしても「みんなの仕事」
っていうのが発生します。
みんなの仕事は何かと言うと、
誰にとっても自分の仕事のような、
自分の仕事ではないような、
でもだれかがやらなきゃならないような仕事のことです。
たとえば、道端に落ちている
空き缶拾いとか
職場の便所掃除とかですね。
清掃専門の人を雇っている
職場もあるかもしれませんが
たとえそういう掃除系の仕事が
なかったとしても、
誰がやるか宙ぶらりん
になってる仕事ってどうしても
発生してしまいますよね。
「自分の仕事」と「他人の仕事」
の間にどうしても
「みんなの仕事」はあるものです。
このように、仕事ってのは
上手く切り分けきれないので
やっぱり本質的には
「みんな」でやるものなんだと
思わされます。
ちなみに、この「みんなの仕事」をやる人には
こんなおまけがついてきます。
それは「みんながくる前にオフィスを掃除して、みんなが帰った後にお茶碗を洗っておく」ような「雪かき」仕事です。でもそれができる人間しか「場を主宰する」ことはできません。絶対に。
『困難な成熟』
ここでは「雪かき」仕事と言っていますが、
オフィスの掃除とかお茶碗洗うとか、
いわゆる「みんなの仕事」をする人は
「場を主宰する」
ことができるそうです。
これは場、
つまりはそこの集団全体に底流しているものを
コントロールできるようになる、ということです。
これは言い換えると、
その場全体の責任を負うということだそうです。
さっきの餅をこねる例で言えば、
あんこも餅も両方に責任をもって
しっかりプロデューサーになるということです。
責任をもつと決めた人が決定権をもつので、
コントロールできる、
プロデュースできるというわけです。
イメージしづらいと思うので、
プロデューサーには場を整える責任がある
という事例が挙げられているので
こちらを読んでください↓
でも、そういう「場の透明性」とか「声の通りの良さ」とか」声の通りの良さ」とか「コミュニケーションの円滑さ」のようなメタレベルの出来事を見ているのはプロデューサーだけなんです。だから誰も気がつかない床のゴミにプロデューサーが最初に気がつく。
『困難な成熟』
プロデューサーには仕事が円滑
に進むように場を整える責任が
あります。
でも、ここで言う場を整えるとは
誰にとっても分かるようなことをするのではなくて、
ゴミを拾うことでメタレベルの場が立ち上がるんです。
ゴミに気づいて拾うことで
今まで見えていなかった
「場」が立ち上がる感じですね。
でもこれに対して
消費者マインドオンリーで行く人は
自分の仕事にしか興味がないわけなので
集団全体を主宰するというのが
どれほどメタレベルで
自分の幅を広げることになるのか
いつまでも分からないままなんですよね。
これは別に自分ひとりで仕事
するのが悪いって言ってるわけではなくて
働くことは本来集団的なものなんだ、
っていうふうに理解した上で
働いた方が仕事しやすくなるかも
しれませんよ、という話です。
感想
けっこう耳が痛い話が続いたなと思ってます(-_-;)
私は自分で自分の仕事をプロデュースしたり
マネジメントできない人ですし、
自分宛にちゃんと指示が出されないと
仕事ができないタイプの人です。
すでに回っている既存の集団や組織に
自分をキャッチアップさせるっていう
意識が割とない人なので
マインドセットする
いい機会になったと思ってます(笑)
現に今は携帯電話をはじめとして
自分個人が使いやすいように
カスタマイズされるのが当たり前に
なってきてますし、
既存のシステムや、
ものごとから学んでいく姿勢を
忘れてしまいがちだなと思います。
ちなみに、これは個人が全体にむりやり
キャッチアップすることが美徳だって
言いたいわけではないし、
「みんなのためを思って行動しましょう」
的なことでもなくて
現にそうやって学んでいく姿勢でいた方が
自然にかなっていて気持ちいいかもよ~ということです。
そっちにマインドセットした方が
「場を主宰する」ことができるし
仕事のないところに仕事を見つけるっていう
本来の仕事の仕方ができるんだなと思いました。
そして、まとめていて思ったのは、
「消費者マインド」を超えて、
集団でものごとを捉えるマインドは
どうしたら身につけられるのかな?
と今回疑問に思いました。
でもこれに関してはこれだろうという
予感だけはありまして、
内田さんの言う「複素的身体性」
っていうのがカギになってくるんじゃないかと思っております。
集団レベルでの身体感のことなんですが
それは今回「場を主宰する」話で出てきたような、
メタレベルに場を引き上げる話と共通します。
ですが…
これはまた長くなりますので
次回にまわしたいと思います〜
内田樹『ひとりでは生きられないのも芸のうち』文芸春秋、2011年
内田樹『下流志向 学ばないこどもたち 働かない若者たち』講談社、2013年
内田樹『困難な成熟』夜間飛行、2017年
内田樹『街場の共同体論』潮出版社、2014年
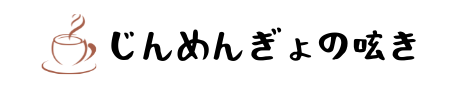
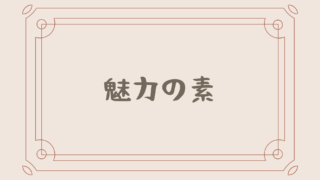
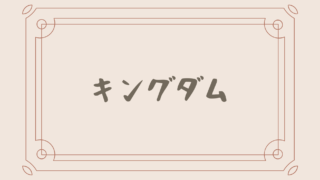
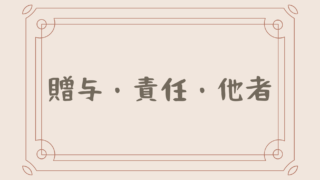
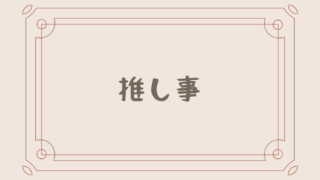
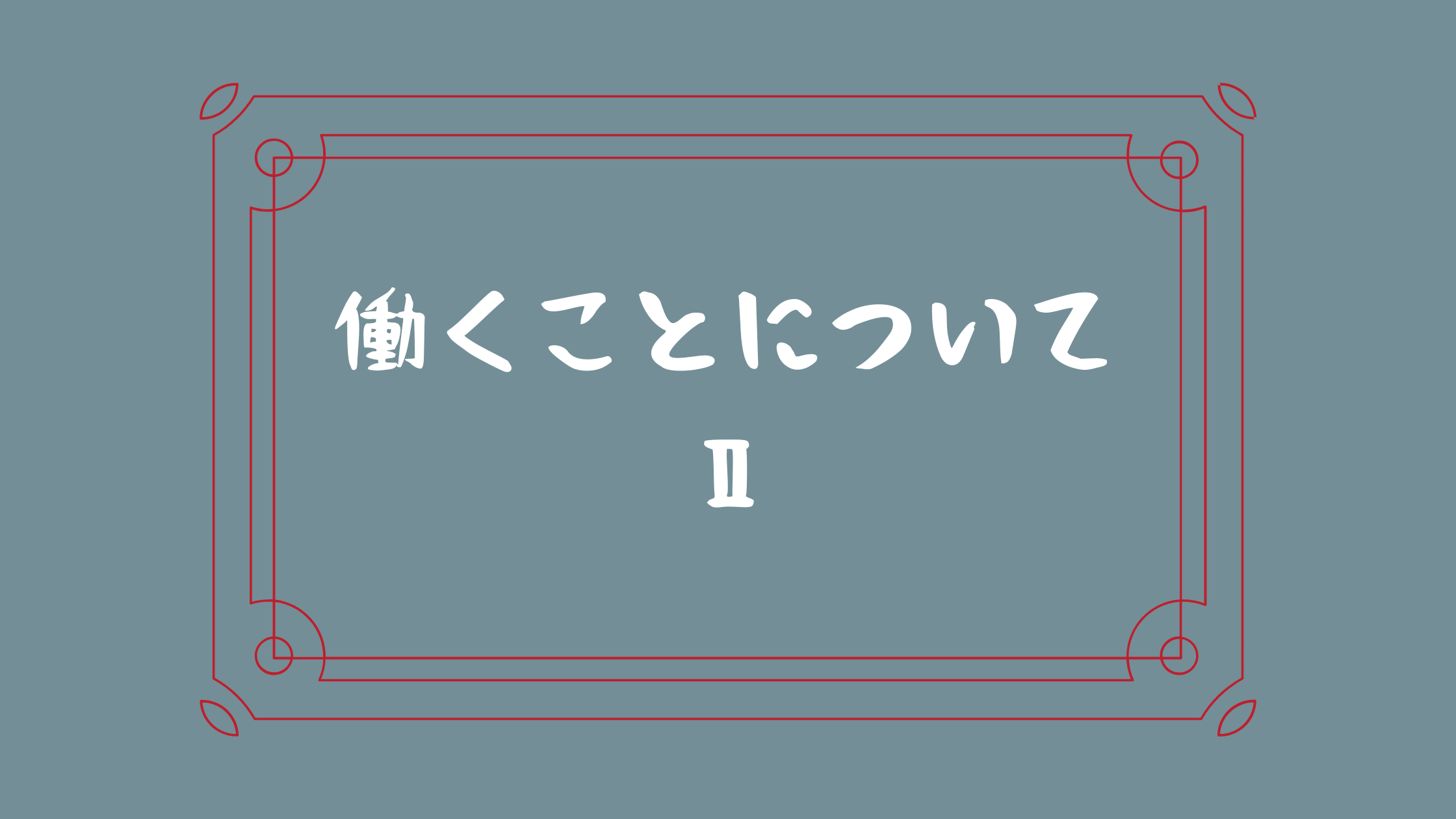

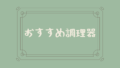

コメント