最近、自立について考えています。
それは何を隠そう私自身が
「自立してないなー」と思うからです。
どういうところでそう思うかといいますと、
周りの友人、知人と比較して、
「なんて私は仕事ができないんだろう!」
と思うことが多いからです。
私と同じ30代になると、
自分で仕事をつくって
自分で仕事を回している人が多くて
私みたいに指示を具体的に出してもらって
誰でもできるような仕事を与えられて、
という人はあまりいないなと思いまして…
へたすると起業してたり、
起業してなくてもなんかプロジェクトを
立ち上げてたりとか…
とにかく、
「どこにいっても
なんとか仕事にありつける」
タイプの人が周りにちらほらいます。
で、それにひきかえ私は…
と反省することがこのごろ多くて、
一度この「自立」について、
あとはその反対の「依存」について
考えてみたいと思っています。
自立は依存先を増やすこと
自立と依存について考える時によく挙げられるのが、
脳性麻痺を持っておられ、
障害と社会の研究をされている
熊谷晋一郎さんのこちらの言葉です。
「自立」とは、依存しなくなることだと思われがちです。でも、そうではありません。「依存先を増やしていくこと」こそが、自立なのです。これは障害の有無にかかわらず、すべての人に通じる普遍的なことだと、私は思います。
全国大学生協連HP https://www.univcoop.or.jp/parents/kyosai/parents_guide01.html
熊谷さんは2011年の東日本大震災の時に、
エレベーターが使えず建物の5階から
逃げ遅れた経験をされています。
熊谷さんは車いすで移動されるので
エレベーターしか逃げる手段がありませんでした。
熊谷さん以外の健常者の人は
階段やはしごで逃げることができ、
エレベータ―含めて
「三つも依存先がある」のですが
熊谷さん自身はエレベータしか
「依存先」がありませんでした。
この経験から、
自立とは依存していないことなのではなく、
依存先が多いことが
自立していることなのだと
気づかれたそうです。
※参照→東京人権啓発センターHP
https://www.tokyo-jinken.or.jp/site/tokyojinken/tj-56-interview.html
これを聞いて私は結構発想の逆転だなと
思って驚きました( ゚Д゚)
自立は「自分でなんでもできること」、
「依存しないこと」
だとぼんやり思ってたので
そうではなかったんだ!
という新鮮さがありましたね。
自立してる人というのは、
誰かを頼ったり、頼られながら
器用に生きている人のことを言うのだなと思います。
依存先を一つに限定せず
上手く頼れるかどうかがポイントなんだな、と思いました。
上手く依存するには?
自立することは依存先を増やすことなのだとしたら
冒頭で私が挙げた自立できないという
悩みに対して、どういう見方ができるでしょうか。
もう少し自立できない悩みを詳しくお伝えすると、
私は具体的な指示やマニュアルがないと
仕事ができないタイプだと自他ともに認めておりまして
いわゆる指示待ち人間でございます(-_-;)
なぜ指示待ち状態になることが多いのかというと、
ざっくり仕事の全体像が分かっていて、
だいたい何がしたいのか掴めていても
具体的な行動に落とし込んだり、
「じゃあどうするのか」というところまで
話を詰めていくことができません。
それで一旦傍において考えていたり、
おろおろしていると、
デキル人がちゃっちゃと仕事を進めてくれて
それで仕事が完結するのはいいんですけど、
私はデキる人に依存している
という評価をされて終わる、、、
というパターンが繰り返されます。
でも、これを先ほどの
熊谷さんの言葉にあてはめて考えてみると、
依存先、あるいは依存の仕方が限定されてて
「上手く依存できていない」
という見方ができるのかなと思いました。
依存先を増やすなどして、
「上手く依存すること」が
大事なんだなと思います。
熊谷さんの言うように依存先を多くしても
いいですし、
依存する方もされる方も
双方にとって違和感のない
「依存」をすることがカギなんだと思います。
では、「上手く依存する」には
どうしたらいいのでしょうか…
と言っても
これに関してまだ明確にこうすればいいと
言えるわけではないので
それ以上は言えないのですが…
少なくとも先の私の例で言えば、
指示を限定的な仕方で受け取っている
からこそ依存してる感じが
余計出るんだと思います。
つまり、具体的に
「これをこうして…」とか
「あの書類のここを訂正して」とか
分かりやすいメッセージ
をひたすら待ってるだけの
「受け身」の姿勢ではなくて、
その人とのあいだに生じている
空気感とか、
「声にならない声」とか
身体レベルでの呼びかけとか
そういうところも察知してあげて
仕事ができたら
今まで通りの「受け身」な態度で
指示待ち人間だ、という評価を
受けなくて済むのかなぁ
なんて思ったり思わなかったり( 一一)
要するに、
相手からの指示に依存しているのであれば、
いっそ色んな形で相手から
「指示」を受け取って依存してしまおう!
という考え方の切り替えこそが
必要なのかなと思いました。
それが「依存先(or依存の仕方)を増やす」
ということなんだと理解しています。
まとめのようなもの
自立したい、
という気持ちがあるので
今回色々考えてみたんですけど
そもそもなんで自立しなきゃ
いけないと思うのかを
考えてなかったなーとも思いました。
もちろん職場で上司とかに
そう言われるから、
とか
自立してる(依存先が多い)
方が色んなことできるし
困ることもこの先少ないかなと思ったので
自立したいなと思ったんですけど、
うーん…
でもそれだけでもない気がしています。
次回、
もし気が向いたらそういうことも
考えていきたいと思います。
あとは、冒頭で挙げた、
自分でプロジェクト立ち上げたり
起業したりしてる人と
私みたいな人ととでは
いったいどこがどう違うのか
ってのも考えておかなきゃならない
ような気がしました。
やっぱり単に「自立している人と
依存している人」
というだけにとどまらない
何かがあると思うので
ここらへんも次回の宿題にしたいなと
思います。
以上です~
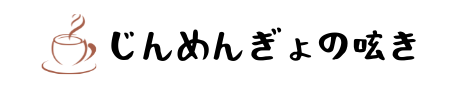
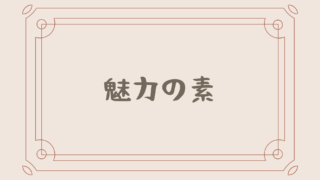
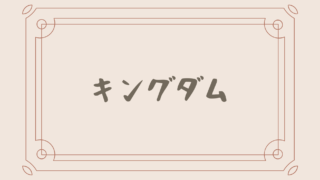
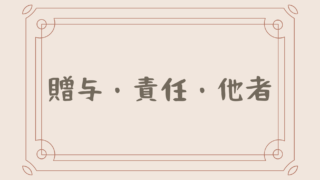
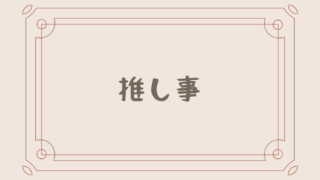



コメント